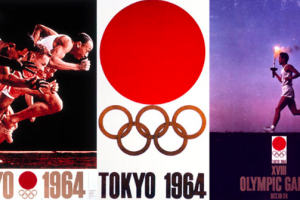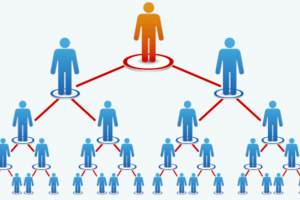今日のテーマは、『社会保障に保有資産要件が付される時代が、いよいよ現実になろうとしている』です。
特に意図していませんでしたが、今週は重点的に社会保障分野の情報発信をすることになりました。
18日には『窓口負担3割の高齢者を増やすことが、現役世代の負担減に繋がらないジレンマ』と題して、日本政府が高齢者の医療費・自己負担3割の対象者拡大を画策中であることをご紹介しました。
これには、現行制度のまま移行すると返って現役世代の負担を増やしてしまうというジレンマが存在していますが、ここではそれについての議論を一旦脇に置いておこうと思います。
兎に角、健康保険(医療)・介護分野に関わらず、これからは被保険者の年齢に関係なく『自己負担率3割』になることがスタンダード化していく時代がやってくると想像します。
もちろん、その水準(自己負担率3割)は十分とは言い切れない為、その上のフェーズに突入する可能性もあると思いますが。
また、最近では、自己負担率3割の対象者を拡大する議論の中で新しい話題も出てきています。
これまで、それは主に年金等の収入の大小により判断されて来ましたが、高齢者については各々の保有資産にも着目して、金融所得も含めて社会保険料・負担率を決定していくという考え方です。
実は、日本政府は2020年代後半の実現を目指して、すでに決定稿として既定路線で進めています。
ちなみに、金融所得とは株式・投資信託・債券等の金融商品から得られる収入の総称で、利子や配当に加えて譲渡益(売却益:キャピタルゲイン)等が挙げられます。
仮に、定年退職までにある程度(数千万円〜1億円ほど)の規模の金融資産を築いていたとしたら、例外なく、ほぼ確実に社会保険料の算定にネガティブな(?)影響を与えると考えられます。
個人的に興味を持って見ているのは『新NISA』で、現時点では明言されていませんが、将来的にはここにある金融資産も算定対象になる可能性が高いものと推測しています。
新NISA制度は、日本政府・金融庁の肝煎りで2024年からスタートした社会保障対策の注力施策。
従来のルールを刷新して制度は恒久化され、拠出することができる総額もつみたて投資枠(投信)・成長投資枠(個別銘柄)を合わせて1800万円までと大幅に引き上げられました。
もちろん、これだけで『億り人』になることはほぼ不可能ですが、3000万円ー5000万円ほどの資産であれば構築する人たちは今後続出してくるだろうと予想しています。
その方々に対して、利子・配当・譲渡益(売却益)が非課税で受け取れるとなれば、原則のルールは変更されておらず、決してウソはついていないことになりますよね。
しかし、それらの収入が社会保険料の算定や免除基準の判定に用いられるとなれば、私たちが当初にイメージしていたものから異なるものになるということも事実です。
2014年に情報発信をスタートして以来、10年以上前から、私は日本の社会保障制度に『保有資産要件』が付される時代が到来するであろうと予見していました。
今日取り上げた健康保険(医療)・介護分野だけでなく、一定基準以上の金融(純)資産を保有している人たちは、年金すら削減されてしまう時代がやって来るのではないかと。
以前は夢物語のように捉えられていましたが、それが今、いよいよ現実のものになろうとしています。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太