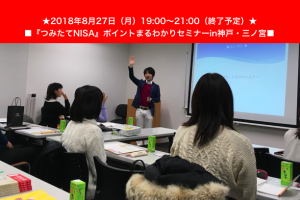今日のテーマは、『テクノロジーが進化した今、私たちは高度に複雑化した社会を生きている』です。
1971年、基軸通貨・米ドルは金(ゴールド)と兌換する権利を自ら手放しましたが、これにより世界全体として金本位制は終焉を迎えて、以降、金融の世界は複雑化を極めていくことになります。
それから半世紀が過ぎた現代は、生み出される価値以上のマネーが供給されることが常態化しており、地球上の金融規模もビッグバン(宇宙爆発)が如く実体経済と大きく乖離して膨張し続けています。
私たちは、相対で現金をやり取りする伝統的(アナログ)な取引と並行して、バーチャル空間でそれとは異なるルールでマネー・ゲームが行われる、冷静に考えると摩訶不思議な世界を生きている、、、、
そんなことを考えていた折、某・著名経済学者が提唱する興味深い考察に触れる機会がありました。
それは、古典的な一物一価制(*)が社会全体として崩壊して、人それぞれ提示される価格が異なり、遂には『お金』というアナログ・ツールの存在がなくなってしまう社会を予見したものです。
*一つのモノ・サービスに対して、相手の属性に関係なく同じ値段が付されるシステムのこと。
例えば、私が今日の昼食として選択した天丼は『1000円』でしたが、年収500万円の会社員であれ、私であれ、総資産100億円を超える大富豪であれまったく同じ金額の負担が求められます。
それは、値段がコスト(材料費・光熱費・人件費等)積上げ方式で決定されているという理由もありますが、相手の属性(主に経済的な裕福度)が分からないという点も決して無関係ではありません。
もしも、先ほどの『天丼』の事例で、総資産100億円を超える大富豪からは5000円(通常価格の5倍)を徴収したとしても、その体験から得る相手の満足度はほとんど変わらないと想像します。
対して、近年、日本国内でも急速に進むキャッシュレス決済は情報空間で行われる取引のため(過去の取引事例からの推測も含めて)相手の属性はアナログよりも遥かに把握しやすくなります。
ここでは、アナログ空間と比較して一物一価で取引をする必要性は極めて低くなり、モノ・サービスの提供者サイドが、相手を見ながら『後出しジャンケン』的に価格を提示することが可能になる。
実際に、米国内でアマゾンに次ぐECプラットフォームを構築するWayfair社は、閲覧者の属性により提示する価格を変更するシステムを導入したことをオフィシャルに公表しています。
普段、私たちが利用しているバーチャル空間の取引についても、既に、それが導入されていると考えられるサービスは存在していますよね。
例えば、私は、公私とも宿泊予約に特定のECプラットフォームを利用していますが、その理由は、最上位ランクに与えられる付帯オプションや割引率に魅力を感じているからです。
ただし、盲目的にならぬよう、宿泊予約をする際は代表的な他社サイトも幾つかチェックして、そのサイトを利用することに経済的合理性があるかを確認するようにしています。
それでも、セルサイド(運営会社)には『ある程度の宿泊費を支払う人間』と把握されていることも事実であり、果たして本当に『最安値』を提示されているかはブラックボックスのため分かりません。
もちろん、バーチャル空間であれ、リアル空間と同様に市場の調整機能が働くことは確かです。
これは、現実世界で同じモノがA店・B店で価格差ある状態で売られていたら、より安価な方(仮にA店)にお客さんは集まることになり、B店も価格を揃える方向に動くことになるのと同じこと。
それでも、前世紀までのシンプルな時代と比較して、現代が複雑化していることは間違いありません。
パラメータ(変数)が数多存在していて、画一的な尺度・価値基準がなくなってきていることも、私たちはきちんと意識しておく方が良いと考えます。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太