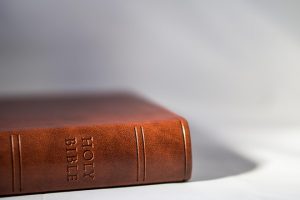今日のテーマは、『上昇する国債利回り、サブプライム・ショック以来の高水準は何を意味するか』です。
昨日、債券市場では長期金利(日本国債10年もの利回り)が一時1.595%を付ける場面があり、2008年のサブプライム・ショック以来、約17年ぶりとなる数字を記録しました。
その後多少の変動はあるものの、文章を執筆している正午時点で同水準にあります。
もちろん、日銀・黒田政権下で展開された『ゼロ金利』こそ異常事態だった訳ですが、ここまで急速に『金利ある世界』が復活することは少しだけ不気味さを感じてしまいます。
先ず、債券の基本中の基本だけ整理しておくと、取引価格と金利(利回り)は逆相関の関係にある。
これは、理屈を考えればシンプルに理解することが出来て、人気のある債券(高い格付け等)は需要と供給が前者(需要)サイドに偏るため必然的に価格が押し上げられていきます。
結果、分母である価格が上昇することから、金利(利回り)は低下するというロジックです。
言い換えれば、誰もが欲しがる優良債券は金利(利回り)が低くても購入されるということ。
反対に、需給バランスが後者(供給)サイドに偏る不人気債券は、取引価格も低調になり、必然的に金利(利回り)は上昇することになるのです。
今回、日本国債の利回り上昇を話題にしていますが、それは即ち、市場全体として『売り圧力』が優勢にあり取引価格が下落傾向にあるということ。
なぜ、そのような動向になっているのでしょうか?
それは、今週末(7月20日)に投票を控える参院選と関係していて、どのような結果が出ようとも、これを機に拡張的な財政政策が選択される可能性が高まっているからです。
ご存知の通り、日本は現時点で対GDP(国内総生産)250%超の巨額債務を抱えており、過去にデフォルトした実績があることも考慮されてか、国債の信用格付けはもともと高くありません。
その上、今後も『借金体質』の改善を見込むことが出来ないとなれば、長期的視点でそれ(日本国債)を手放そうと考える人が増えたとしても不思議ではありませんよね。
先ほど説明した通り、不人気(低い格付)債券は価格が下落し、利回りが上昇する傾向にありますから、今起きている現象は理屈的にも成立している訳です。
それでは、日本の長期金利(10年もの国債利回り)1.595%は、世界的に見て高い水準にあると言えるのでしょうか?
一つの基準として、米国10年債の利回りは現在4%台半ば(4.480%前後)で推移しており、日本国債のそれとは実に3%近くの差が存在しています。
しかし、両者の決定的な違いは、米国債は市場取引により調整機能が働いて成立した数字であるのに対して、日本のそれは中央銀行(日銀)の買い支えによりマスキングされたものであるという点。
つまり、コントロールを仕掛けている人間も含めて、誰も実態を理解できないということです。
私の記事では頻出しますが、投資の神様であるウォーレン・バフェット氏は過去に『潮が引いて初めて、誰が裸で泳いでいたのかが分かる』という言葉を残しています。
日本の状況はそれと同じようなもので、潮が引いて(マスキングが外れて)初めて、国債の数字を通した国家財政の正しい評価が得られることになります。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太