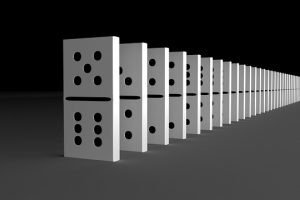今日のテーマは、『学歴社会が崩壊した今、日本においてそれは無意味なものになったのか』です。
最近、立て続けに『学歴』をテーマとしたニュース・フィードを目にする機会があり、改めてそれ(学歴)について考えてみました。
共通認識を整理しておくと、日本において『学歴社会の崩壊』が叫ばれて久しいですよね。
それ(学歴)は決して社会的・経済的成功を保証するものではなく、出身大学がどこであるかにより、その後の人生を完全に占うことは不可能であると。
確かに、いわゆる偏差値の高い有名大学を卒業しても経済的・社会的地位に恵まれない人が存在するのは事実ですが、その『例外』を以って全体の話に拡大解釈するのは暴論甚だしいと感じています。
もしかしたら、昭和の時代はもっと色濃かったものが薄まりつつあるというニュアンスなのかも知れませんが、1980年代に生まれ、平成の半ばに社会人になった私としては想像の域を出ません。
仮にそうだとしても(昭和時代より薄まったとしても)、学歴社会の崩壊が叫ばれ始めた平成以降の時代でさえ、私自身は少なからず『学歴』というものの恩恵に与ってきたと実感しています。
先ず初めに断っておきたいことは、それ(学歴)を手に入れる云々の問題以前に、学生時代だけに限らず人生を通して絶対的に『勉強』はした方が良いということです。
中学時代に通っていた塾の代表は『なぜ勉強するのかと問われれば、人生を豊かに生きるためだ』と話していましたが、自らが40歳を超えた今、この言葉には激しく同意しています。
もちろん、この言葉は社会的・経済的成功を含むかも知れませんが、自らが学び・体得したことで実務的・文化的にも豊かに生活できるようになるという意味も多分に含まれると考えます。
そして、主体的に『学ぶ』ことが習慣化されている人間は、必然的に実用性のある『学歴』も手に入れるため、人生を通して様々な面で『豊かに生きる』ことが可能になるのです。
また、先ほどは『経済的成功』を一旦脇に置いて話を進めましたが、現実世界を生きていく上で『お金』を無視することは出来ませんよね。
実用性のある『学歴』を手に入れることで、経済的成功を収める確率も言わずもがな高まります。
例えば、私自身は新卒で製薬企業に入社して働いた経験がありますが、当時、その企業は平均年収1200万円、新卒初任給も年間600万円に迫るほどの優良企業でした。
さらに言えば、福利厚生の名の下に表に出てこない(課税されない)手厚すぎる収入が存在しており、日常生活のコストはそちらで殆どカバーできた上で、前述の『給与』が支払われていた。
一度、それら(福利厚生)も含めて現金換算して計算したことがありましたが、大学を卒業したばかりの若造が、実質的には『年収1000万円』に迫る恩恵に与っていたことには驚きました。
その結果、私も含めた同期入社の大多数の金銭感覚は壊滅的に崩壊してしまい、入社後1〜2年目の若造が外車を乗り回しながら営業するという事態が全国的に横行することになったのですが。
話を本題に戻すと、私たち営業職の同期166名のうち、関関同立(関西学院・関西・同志社・立命館)やGMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)以下の大学出身者は皆無です。
もしかしたら、選考の過程でたまたま(?)そうなったのかも知れませんが、常識的に考えれば、エントリーシートを提出した段階で『学歴フィルター』が存在していたと想像する方が自然です。
もちろん、上を見れば際限がありませんが、ある程度の『学歴』を保有していなければ、足を踏み入れることすら叶わない領域が存在していることは確かな事実なのです。
間違って伝わって欲しくないのは、ひとつの指標である『学歴』を絶対視する訳では決してなくて、自ら主体的に学ぶことを習慣化していれば、ある程度のそれは手に入れられるということ。
そして、『勉強』を通して努力を積み上げることで、現実世界で『問題・課題』に直面したとき、それにどのようにアプローチして解決・克服するかという思考プロセスを体得できるということ。
先ずはゴール(到達目標)を明確化して、事象全体を大枠で捉えて、目標を実現するための要点を因数分解して、優先順位をつけて取捨選択して具体的に実行していく。
このプロセスは社会に出てからの問題解決のアプローチと同じですが、いわゆるFラン大学出身者と高学歴を保有している人たち、どちらがそれを実践していくことが出来るでしょうか。
2025年、元号が『令和』に突入して暫く経つ今尚、日本に『学歴社会』は確実に存在しています。
もちろん、それは完璧ではありませんが、社会がその人物を『合理的』に評価するための有効な指標の一つであることに変わりはありません。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太