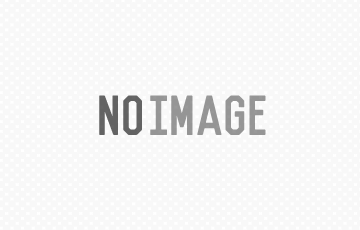今日のテーマは、『資産形成(投資)において、上手くいっているの判断が簡単ではない理由』です。
元来、日本人は金融・経済、および投資には疎い国民性と言われています。
今から40年ほど昔のことになりますが、不動産市場・株式市場を主戦場として展開されて、その後に大崩壊した『バブル』の痛みの経験が未だに尾を引いているのかも知れません。
幸か不幸か、昨年(2024年)スタートした新NISAをきっかけに、国内の投資家人口は久々に大きく増加に転じていますが、前述した民族的な気質はそれほど変化していないと想像します。
資産形成(投資)に限らずすべての物ごとに共通して、全体のプレーヤーが増加することは、それがそのまま玄人の増加や対象分野の成熟を意味するわけではないからです。
時々、私がファイナンシャル・プランナー資格を有して、投資をアドバイスする立場にあることを知った人たちから『投資は上手くいってますか?』と質問されることがあります。
正直、この類の質問は面倒なので、いつも煙に巻いて去(い)なしてしまうのですが。
何故なら、自分としては『上手くいっている』と判断する投資行動でも、一般の方々、特に投資初心者がイメージするそれとは観念そのものが異なり、話しても理解することが出来ないと考えるからです。
例えば、株式市場で『個別銘柄』を対象に投資するケースを考えてみましょう。
一般の方々(特に初心者)がイメージする『上手くいく』とは、先見の明をもって『掘り出し物』を発掘し、すべてとは言わないまでも2ー3割がテンバガー(株価10倍銘柄)に成長するというもの。
結果、1ー2年というわずかな期間で総資産は3倍、4倍、若しくはそれ以上に膨れ上がるというストーリーですが、そのような話は射幸心が強く刺激されて、聞いているだけでワクワクしますよね。
しかし、現実世界ではそうそう簡単に『宝くじ』に当たるはずもなく、仮に運良く当てられたとしても、再現性をもって継続的に当て続けることは不可能です。
私自身、目下、新NISAを活用して個別銘柄投資を実行中ですが、テンバガー(掘り出し物)の発掘などは端から捨てて、出資額に対して年率4ー5%の配当を得ることを目的に実践しています。
投資対象となる銘柄は、原則として東証プライム市場に上場する大企業で、数多くのアナリストと投資家が常に注目しているため、刹那的な観点で株価のミスプライスが起こりえないもの。
また、事業規模は年間1000億円を最低基準として、売上高、利益率・純利益(額)、配当の金額についても年毎に大きく変動しない(実際はほぼ変動なし)銘柄を厳選してセレクトしています。
その結果、制度開始から約1年半が経過した現時点、キャピタル評価(*1)は1%のマイナスながら、本来の目的である配当収入は出資総額に対して『+約3.8%』を達成しているのです(*2)。
*1:キャピタル評価は保有する株式の時価総額を、それを取得するのに要した出資総額で除して算出しています。(1ー 保有する株式の時価総額 / 出資総額)
*現時点で権利を獲得している配当収入の総額を、全株式を取得するのに要した出資総額で除して算出しています。(獲得した配当収入の総額 / 出資総額 ー1)
ここでは詳細を語ることを避けますが、対象銘柄は非常に底堅いビジネスを展開している企業を厳選したため、長期的な視点で内部留保を積み増していけば『増配』もかなりの確率で発生し得る。
そうなれば、当初目標としていた『年率4ー5%配当』も十分射程圏に捉えられるのです。
更に言えば、キャピタル評価のマイナス1%という数字も、日経平均株価が未だピーク時点から10%超下落して停滞していることを考慮すると順調そのもの。
今後も、環境の変化(対象銘柄の株価が急騰して配当利回りが低くなる等)がなければ順次買い増していくので、株価が急騰していない現在は、配当権を安く入手できる最高の時期と考えられます。
資産形成(投資)が上手くいく・いかないという評価は、唯一無二の絶対的な指標がある訳ではなく、要は、自分自身が『意図していること』が実現できているかで評価することが出来る。
誤解を恐れず言えば、投資において『資産を増やすこと』は想像以上にシンプルです。
しかし、自らが美学と信念を持たなければ、絶対に成し得ないということも事実です。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太