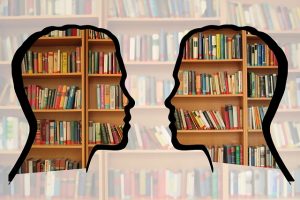今日のテーマは、『社会全体に大きな変化が訪れる前には、常に小さなサインが発されている』です。
先日、社会的には大きなインパクトを与えないものの、個人的には非常に引っ掛かる(興味を惹かれる)報道が流れてきました。
それは、昨年(2024年)度に障害年金の申請をして不支給と判定された人たちが、前年(2023年)度の2倍超、数として3万人にのぼるというもの。
この間(2023年ー2024年)全体の申請者数は20万人程で大きく変化はしておらず、単純に不支給と判定された人たちの割合が倍増したことを意味します。
実に、全体の6人に1人が申請を却下されたことになり、日本年金機構が統計を取りはじめた2019年以降で最大となる見通しです。
少しだけ基本情報を整理すると、障害年金とは、病気やけがで日常生活や仕事が制限されるようになった場合、65歳未満の現役世代も含めて受け取ることができる年金制度。
老齢年金と同様、大きく2つ(基礎年金・厚生年金)に別れており、病気やけがで初めて医師の診療を受けた時点で、国民年金に加入していれば前者、厚生年金に加入していれば後者を請求可能。
また、厚生年金加入者は、障害年金の該当要件よりも軽い障害が残った際に手当金(一時金)を受け取ることもでき、至れる尽くせりの公的なセーフティ・ネットです。
話を戻すと、昨年度、不支給判定を受ける人が急増した理由は明確に公表されていません。
もちろん、内部(日本年金機構)には明確な判定基準・厳格化されたルールがあるのでしょうが、保険商品の加入時同様それが表に出ることは絶対になく、最終的にはブラック・ボックスです。
一部、責任者の配置転換により現場レベルで審査が厳格化されたとの話もありますが、所詮、大きな組織の一責任者レベルの人物に、そこまで大きな権限が与えられているかは甚だ疑問です。
確かに、人事異動は(審査が厳格化された)ひとつのきっかけかも知れませんが、もっと上の立場の人間、機構中枢にいる人たちの命(命令)が下ったと考えるほうが自然です。
冒頭に触れた通り、障害年金の申請者数は年間20万人ほどに留まり、老齢年金の受給者数が約4000万人であることを考慮すると微々たるもの(約2%)です。
つまり、仮に、この分野(障害年金)でドラスティックな変化が起きていたとしても、それが社会全体から大きな注目を集める可能性は極めて低いものになる。
しかし、国民全体から年金保険料を徴収して該当者に支給するというシステムは、私たちが普段から意識している老齢年金制度とまったく同じものなのです。
老齢年金同様、原資が枯渇し始めているのですから、支給を絞り出しても不思議はありません。
異次元レベルの少子高齢化が進行している日本において、私は以前から、公的年金システムは近い将来に破綻するか機能不全に陥ると指摘してきました。
その時は『突然死』のようにやって来るかも知れませんが、そこに至るプロセスでは無数の『小さなサイン』が発信されることになります。
今回の事例も、そのひとつ(サイン)に見えてなりません。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太