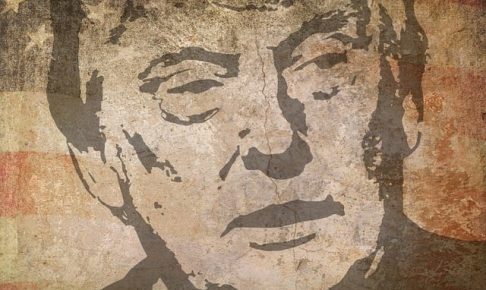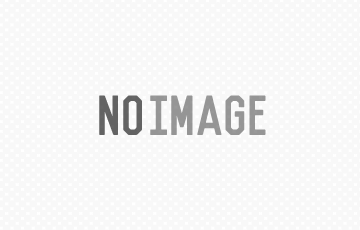今日のテーマは、『回避されたパウエル・ショック、トランプ大統領とFRBの微妙な関係』です。
先週までの乱高下と打って変わって、ここ数日、日米両市場とも堅調に上昇していますね。
米国の代表的な指数であるNYダウ平均株価は、月曜日(21日)からの4日間で5%ほど上昇して一つの節目である4万ドル台を回復しました。
また、それに牽引される形で日経平均株価も3万5000円台後半まで上昇を見せています。
それでも、2週目から3週目にかけての大幅下落分を挽回して、月間最高値である月初めの水準に戻ったと言えばそれまでですが。
いずれにしても、一時的に下落が底を打ったことで市場が落ち着きを取り戻し、穏やかに5月を迎えられるかも知れません。
今回、マーケットが急転・反発した理由の一つは、緊張が走っていた相互関税をめぐる米中貿易摩擦が悲観シナリオを回避して、緩和に向かうとの観測が高まったから。
当然ながら、21世紀の2大大国がお互いに高関税を掛け合う状態で、長期間、世界経済が成立し得るはずがありません。
それ故、相互関税はあくまでディール(取引)のためのツールであり、自国の利益が最大化するよう交渉を進めるためのポーズだと受け取るほうが妥当です。
そして、相場反転のもう一つの理由は、トランプ・米大統領がFRB(連邦準備制度理事会)パウエル議長の解任を翻意したことで社会全体に安心感が広がったこと。
元々、トランプ氏は正式就任以前から利下げ慎重派のパウエル氏に不満を表明しており、大統領に当選した暁には『FRB議長を解任する』という旨の発言を繰り返していました。
しかし、これは冷静に考えれば驚くべき(恐ろしい?)ことで、絶大な権力を持つ大統領と言えど、中央銀行の独立性を脅かすとなれば民主主義国家の根幹すら揺るがす事態になり兼ねない。
まして、それが覇権国・米国ともなれば影響は世界全体に波及し、基軸通貨・米ドルはもちろん、株式・債券をはじめとした米国資産全体の信用すら揺らぐことになります。
事実、パウエル議長の解任が現実味を帯びるにつれて、前述のNYダウ平均株価は今月だけでもピーク時点から約12%もの大幅下落を記録することになりました。
トランプ大統領自身、今尚、慎重派のパウエル議長に不満を抱き続けていることは確実ですが、目の前のトリプル安(ドル・株式・国債)に対処することを優先した形です。
オフィシャルに『(FRB議長解任は)一度も検討していない』と発言してリスクは存在しなかったこととされ、今回のパウエル・ショックは回避されることが決定しました。
しかし、ここまでの説明で理解される通り、本質的な問題は何も解決していません。
パウエル議長が任期を終える2026年(5月)まで、大統領とFRBの微妙な関係は続いていく。
米国内における両者の駆け引きについても、私たちは継続的に注視していく必要がありそうです。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太