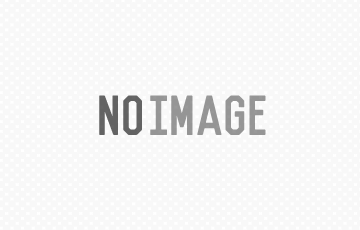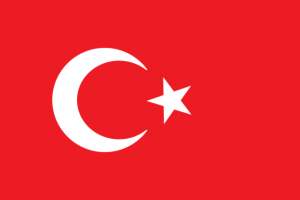今日のテーマは、『真のお金持ちほどシグナリング効果の呪縛から解放されているという真実』です。
先日、ニュース・フィードで興味を惹かれる記事を目にしました。
それは、クレジットカード大手各社が富裕層(高い年会費を支払う人たち?)向けのサービスを強化することで、新規顧客の獲得競争を展開しているというもの。
例えば、JCBは老舗百貨店・松屋とコラボレーションして、東京・銀座に高級カード保有者を対象とした約330平方米の広々とした専用ラウンジを開設したのだとか。
メディアに向けて公開されたそれは花や高級食器が飾られた優雅な空間で、来場者は各々くつろぎながら飲み物やちょっとした茶菓が楽しめるのだと言います。
専用ラウンジを利用することができる対象は年会費5万5千円の最上位カード『ザ・クラス』の保有者のほか、百貨店・松屋の外商顧客の中でも一部の人たちに限定されているとのこと。
関西弁で言えば、対象者が『ドヤ顔』をして入場していく様が想像できますね(笑)
また、ダイナースクラブや三井住友ファイナンシャルも最上位ランクのカード保有者を対象として、神社仏閣の貸し切りや気球型の飛行船に乗る旅行、世界的スポーツイベントの招待を拡充する予定。
実に、あの手この手で顧客ニーズに応える(潜在ニーズを掘り起こす?)ことで、年間5万円から場合によっては10万円を超える年会費の正当性を主張しようとしています。
果たして、これらクレジットカードの上位ランクには本当に価値があるのでしょうか。
個人的には、話題にするクレジットカードのランク分けはビジネスの真理を突いていると感じていて、人間という生き物の弱さの象徴である『シグナリング効果』が上手に利用されています。
シグナリング(シグナルを発する)効果を分かりやすく言い換えた言葉は『見栄』で、意識・無意識に関わらず、人は誰しも自分自身を周りに対して『実力以上』に見せたいと考えています。
もちろん、保有資産や稼ぎ(収入)は主要評価項目の一つですが、額(ひたい)にその金額を書いて歩くわけにはいかず、某著名人のように具体的な数字を公表するのは品格がないとも感じている。
そこで、クレジットカードの上級会員(高い年会費負担者)になり対象カードを保有することで、上手に気品良く(?)シグナルを発信できるようになるのです。
自身も通ってきた道なので分かりますが、女性にモテたい欲求が旺盛な20代、30代の独身男性なら、非常に有効な手段のように感じられますよね(笑)
しかし、40歳を超えて大人になった私はそれに(年会費に見合うだけの)本質的価値があるかを甚だ疑問視しており、ストレートに表現すると『ない』とすら考えています。
例えば、前述したJCBの専用ラウンジの件で言えば、本当に休憩したければそのタイミングで有料の高級ラウンジに入ればいい。
銀座と言えどお茶を飲むだけで5千円も求められるボッタクリ喫茶は存在していないので、月1回(年間12回)のペースで利用したとしても、上位カードの年会費(5.5万円)からお釣りが来ます。
仮に、上位ランクの年会費が値上がりして10万円を超えるようなら、それ(年会費)を上回るメリットを享受する可能性はほぼほぼゼロになりますね。
因みに、このケースにおける『シグナリング』の対義語にあたるのは『経済的合理性』です。
少しだけ言葉を説明するなら、理性を働かせることで浅はかな欲求に打ち勝ち、冷静にリスク・ベネフィットを勘案する能力といったところでしょうか。
ところで、実は、私も事業決済用として一枚だけ某・ゴールドカードを保有していますが、普段通りに利用していれば、年会費に相当する金額を年末にポイント還元してくれるため実質的な負担はゼロ。
それでいてゴールドカードに準ずる各種サービスを提供してくれる訳ですから、現時点では経済的合理性に適った行動をとっていると考えています。
ただし、前述のポイント還元制度がどこかのタイミングで終了してしまうようなら(実質負担額に対するリスク・ベネフィットは検討しますが)速やかにダウングレードするでしょう。
何故なら、仮にクレジットカードを新規作成する場合でも、個人情報が筒抜けになった現代では信用情報を勝手に照会してくれて(年会費無料でも)上限200万円以上のカードを送ってきてくれるから。
その水準のカードを幾つか保有していれば、日常決済に困る場面はほぼありません。
真のお金持ちほど『シグナリング効果』の呪縛から解放されている真実があります。
恐らく、それに囚われているのは、承認欲求が満たされず・消費意欲ばかりが旺盛な年収2000万円未満の方々が大半を占めているのだと想像しています。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太