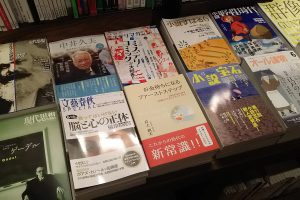今日のテーマは、『介護保険サービス利用の原則2割負担、反発は必至だがそれ以外の道はない』です。
先週11日に開催された財政制度審議会の分科会において、財務省は、それほど遠くない将来に介護保険サービス利用者の自己負担を『原則2割』に変更する必要性があるとの見方を示しました。
少しだけ基本情報を整理すると、介護保険制度は65歳以上の第1号被保険者と40ー64歳の第2号被保険者に大別されており、実際に介護サービスを利用する人たちの大部分を前者(65歳以上:第一号)が占めています。
また、介護サービスの利用総額に対する自己負担率は原則1割とされており、所得要件により例外(2ー3割負担)はあるものの、全体の利用者の約92%がそれに該当しているというのが現状です。
*単身世帯の場合、年金等の収入が年間280万円を超えてくると2割負担となり、さらに年収340万円以上になると3割負担になりますが、現行制度におけるその該当者は全体の8%に留まります。
直近25年間、介護サービス利用者一人あたりの負担額(ひいては介護サービス利用額)はほぼ横ばいで推移していますが、日本全体の介護費用の総額は年間14.3兆円と約4倍の数字にまで激増。
さらに、2040年における日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は35.3%に達すると予測されていますが、その時の介護費総額は現在から倍増した年間27.6兆円までアップします。
保険料に目を移すと、制度が発足した2000年と比較して65歳以上のそれは約2倍に留まっている(?)のに対して、現役世代(40ー64歳)のそれは3倍増とここでも負担を強いられています。
ご存知の通り、少なくとも今後数十年間は異次元レベルの少子高齢化が進展する日本において、高齢者のみならず、現役世代の社会保障負担が爆発的に増加することは火を見るよりも明らかです。
年金・健康保険と同様、介護サービスの分野も高齢者に負担を強いる方向へとシフトする過程では、もちろん大きな反発も予想できますし、実際にそれは起こるだろうと考えます。
しかし、MMT(現代貨幣理論)信奉者が展開する、自国通貨建国債を乱発して財源に充当する方法を除いて、保険料を維持していくためには介護サービス利用者の自己負担を上げるしか道はありません。
ない袖は振れないという言葉がありますが、それは個人であれ国家であれ同じことです。
社会保障システムをドラスティックに変更するという点において、日本は今まさに待ったなしの所にある。
当然、変遷期に生きる日本国民に痛みは伴いますが、私たちは経済的にも精神的にも準備する必要がある時に来ています。
井上耕太事務所(独立系FP事務所)
代表 井上耕太